-
February 28, 2022
-
February 28, 2022
-
July 28, 2022
-
March 24, 2024
-
March 24, 2024
-
March 24, 2024
-
March 24, 2024
-
February 28, 2024
-
February 28, 2024
-
February 28, 2024
-
December 26, 2023
-
October 29, 2022
-
November 26, 2023
-
September 26, 2023
-
October 26, 2023
-
August 30, 2023
-
April 26, 2023
-
May 23, 2023
-
April 26, 2023
-
February 27, 2023
-
November 28, 2022
-
December 26, 2022
-
November 28, 2022
-
October 28, 2022
-
October 29, 2022
-
October 29, 2022
-
September 28, 2022
-
August 30, 2022
-
February 27, 2022
-
December 01, 2021
-
November 30, 2021
-
November 28, 2021
-
November 14, 2021
-
November 13, 2021
-
October 10, 2021
-
August 27, 2021
-
June 21, 2021
-
June 04, 2021
-
May 01, 2021
-
April 28, 2021
-
April 11, 2021
-
March 24, 2021
-
February 21, 2021
-
January 30, 2021
-
January 23, 2021
-
January 19, 2021
-
January 16, 2021
-
December 10, 2020
-
December 01, 2020
-
November 12, 2020
-
September 26, 2020
-
May 22, 2020
-
May 16, 2020
-
May 13, 2020
-
May 10, 2020
-
May 07, 2020
-
April 20, 2020
-
April 18, 2020
-
February 16, 2020
-
December 25, 2019
-
December 25, 2019
-
November 18, 2019
-
October 12, 2019
-
September 25, 2019
-
August 01, 2019
-
July 07, 2019
-
July 03, 2019
-
July 03, 2019
-
February 09, 2019
-
February 03, 2019
-
January 09, 2019
-
November 26, 2018
-
October 15, 2018
-
October 04, 2018
-
August 27, 2018
-
August 18, 2018
-
July 29, 2018
-
July 09, 2018
-
July 09, 2018
-
July 09, 2018
-
July 09, 2018
-
June 13, 2018
-
March 14, 2018
-
March 01, 2018
-
January 13, 2018
-
January 09, 2018
-
December 12, 2017
-
November 25, 2017
-
November 24, 2017
-
November 16, 2017
-
November 11, 2017
-
September 01, 2017
-
August 01, 2017
-
June 30, 2017
-
May 01, 2017
-
May 01, 2017
-
April 18, 2017
-
April 08, 2017
-
April 06, 2017
-
April 04, 2017
-
March 20, 2017
-
March 09, 2017
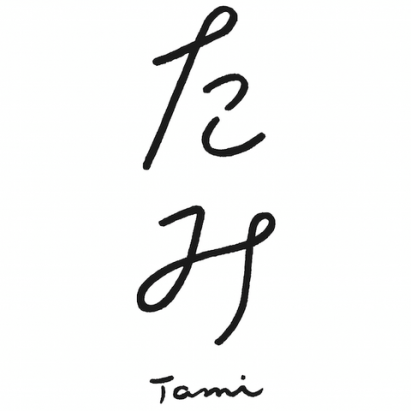


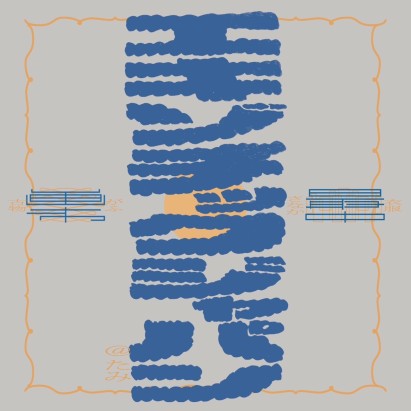
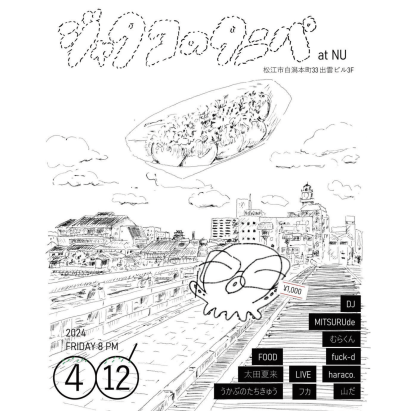
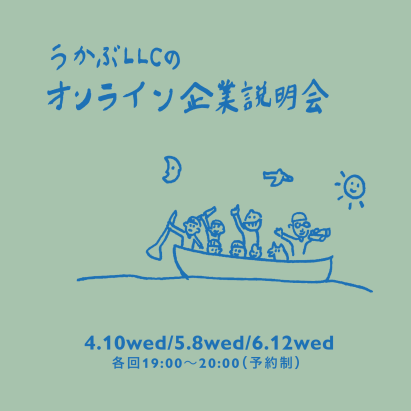
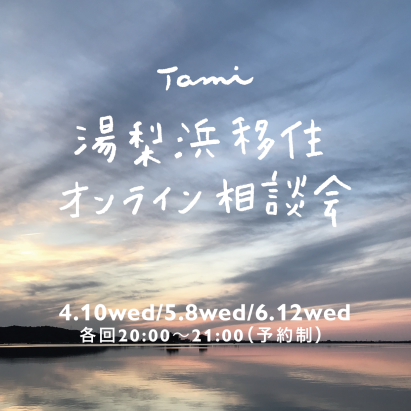
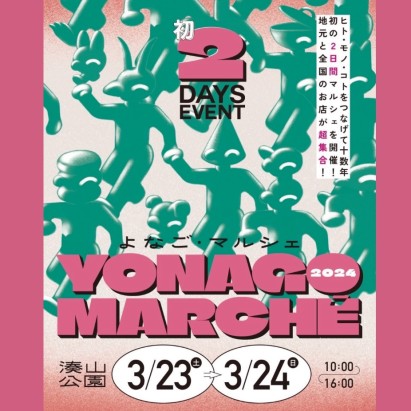

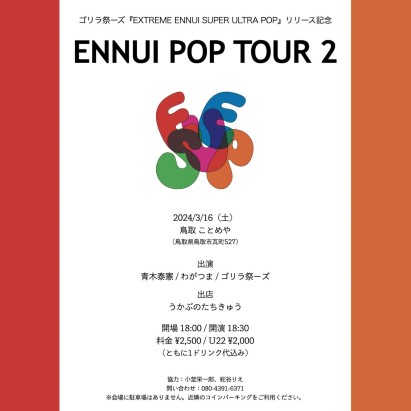
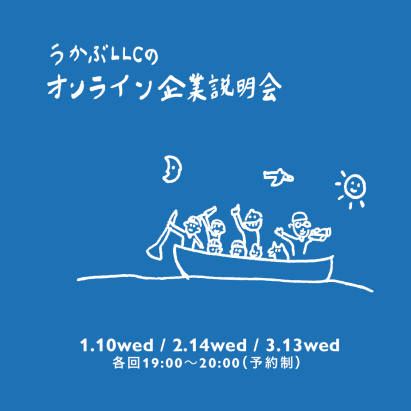










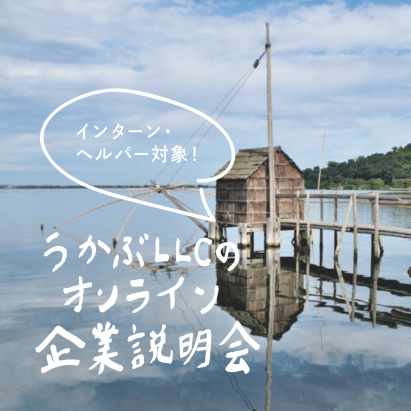

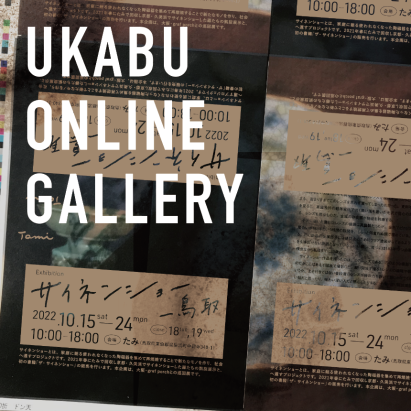
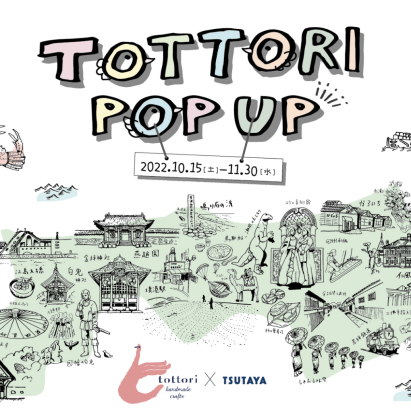

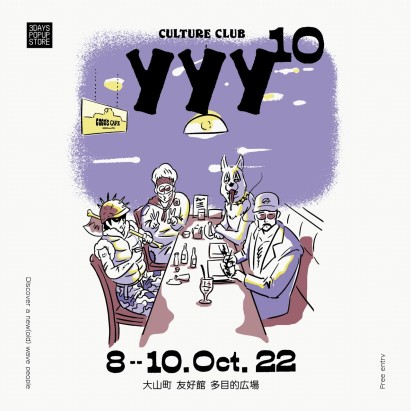
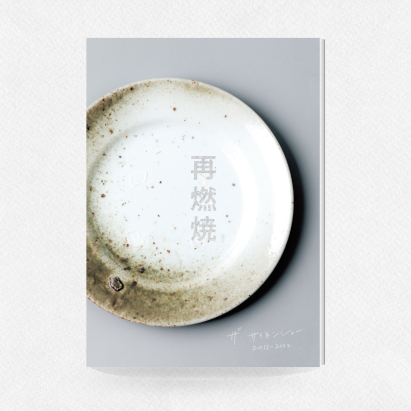

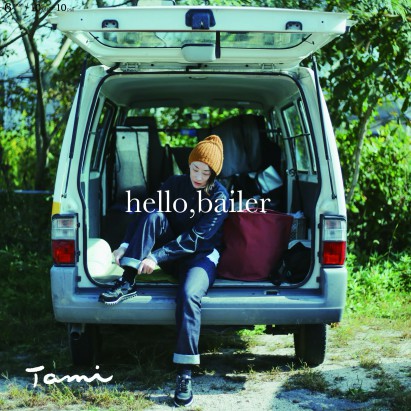

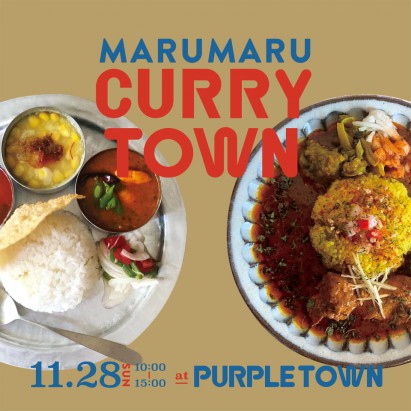
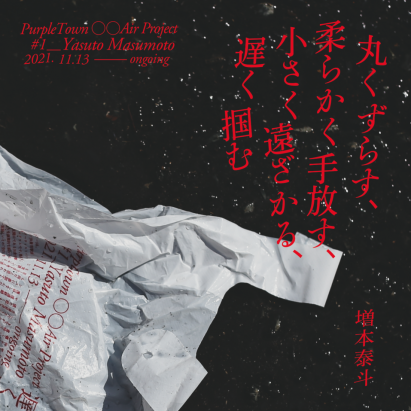







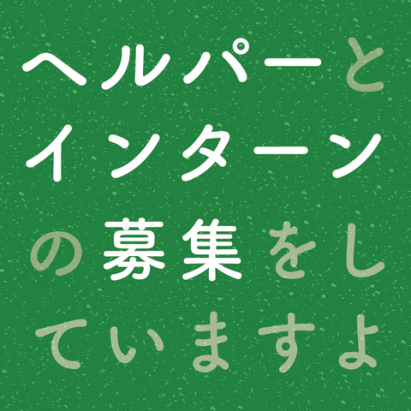




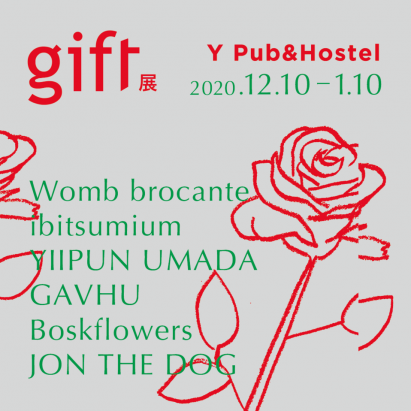





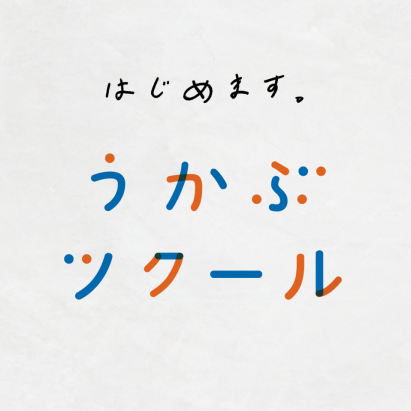












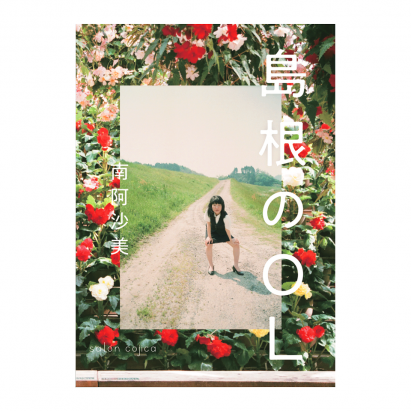




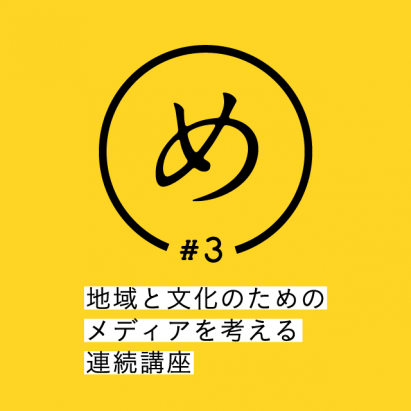

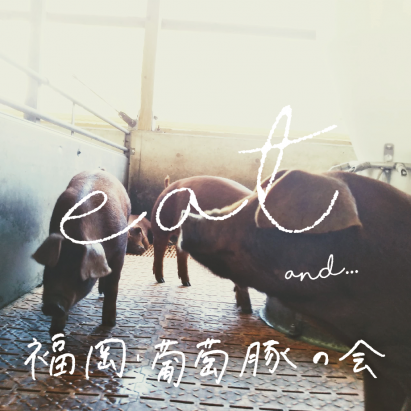


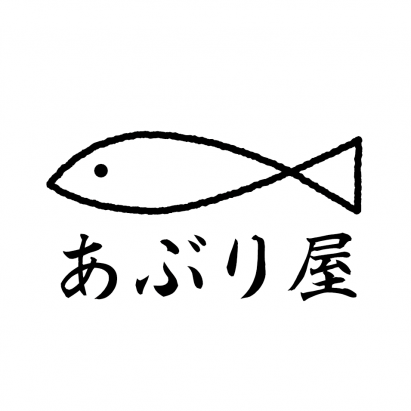

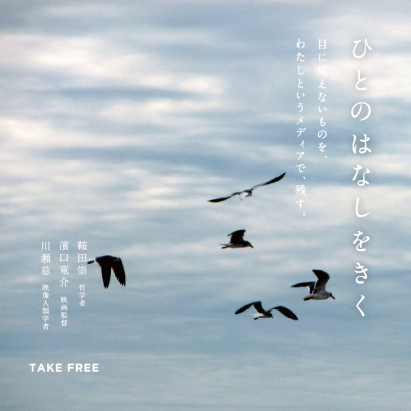


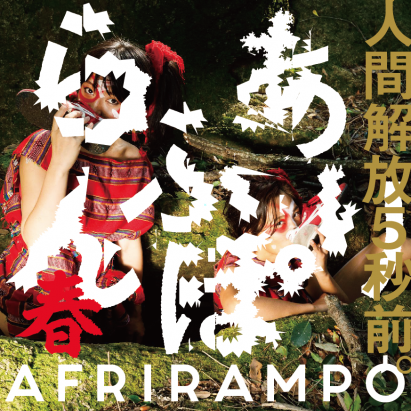


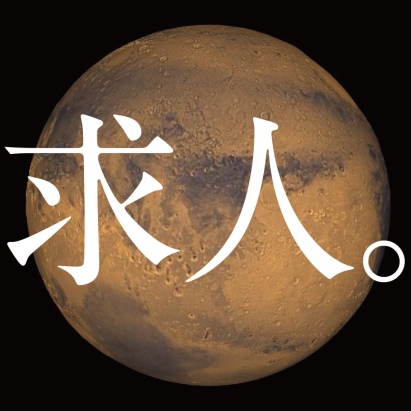


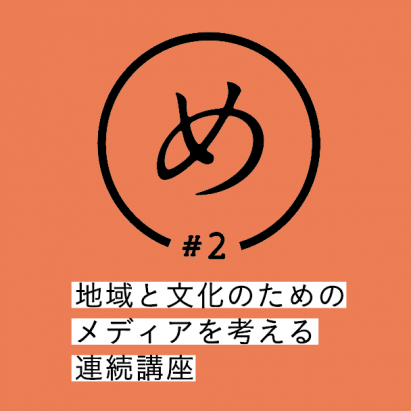

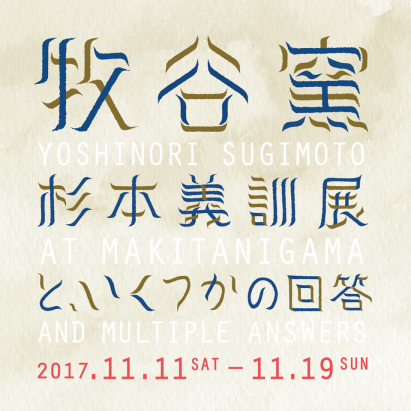
![[ロゴ]トリジュク ロゴ・デザイン [ロゴ]トリジュク ロゴ・デザイン](https://ukabullc.com/wp-content/uploads/2022/01/20180120115705-1-411x411.png)
![[ロゴ]日本酒Bar [ロゴ]日本酒Bar](https://ukabullc.com/wp-content/uploads/2022/01/20180120113152-1-411x411.png)
![[ロゴ] 鳥取夏至祭 [ロゴ] 鳥取夏至祭](https://ukabullc.com/wp-content/uploads/2022/01/20180120113009-1-411x411.png)
![[ロゴ]BOOKTURN 本棚帰郷 [ロゴ]BOOKTURN 本棚帰郷](https://ukabullc.com/wp-content/uploads/2022/01/20180120115230-1-411x411.png)
![[ロゴ]タクシー王子?のとっとり裏道案内 [ロゴ]タクシー王子?のとっとり裏道案内](https://ukabullc.com/wp-content/uploads/2022/01/20180120114525-1-411x411.png)
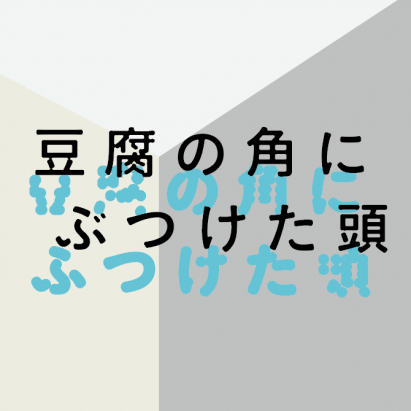


![[デザイン]TOTTO [デザイン]TOTTO](https://ukabullc.com/wp-content/uploads/2022/01/20180120113654-1-411x411.png)

